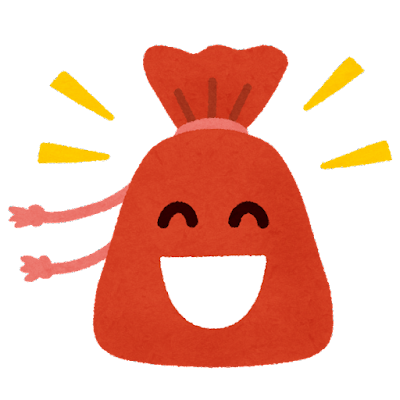「自分の効用関数に他人を組み込む」
これは行動経済学者ダン・アリエリーさんの言葉です。
さっすが学者さんだけあって、難しいこといいますね。
行動経済学は、これまでの経済学に、心理学的なデータも取り入れて研究する学問で、アリエリーさんは「予想通りに不合理」という著作で有名です。
アリエリーさんは、「幸せをつかむ戦略」という本の中で幸せには2つのタイプが有ると言っています。
一つは「海辺に座ってモヒートを飲む」ような「楽な幸せ(タイプ1)」
もう一つは「マラソンを走る」ような「その行為自体には幸福がない幸せ(タイプ2)」
タイプ2は笑っている瞬間がほんの少ししかない、大変だけどやりがいがあることに関わることで得られる幸せと言ってもいいと思います。
子供を生んで育てるとか、資格試験を受けるとか、飲み会の幹事を買って出るとか、そんな感じのものです。
アリエリーさんはこのタイプ2について
「とてつもなく重要で、私達の存在の中核をなすなにか」
と言っています。
冒頭で申し上げたとおり、この本の中でアリエリーさんは
「自分が幸せになるためには自分の効用関数に他人を組み込むことが重要」
と言っています。
もうほんとに難しい言い回しですが「効用関数」というのがなにかわかると、じつはそんなに難しいことは言っていません。
効用関数というのは、例えばパンとコーヒーとか複数のなにか効用(いいこと、満足度)があるものがここあるときに、その組み合わせからどれくらいの満足度になるかを示した関数(計算式)のことです。
U=2x+y
でUが効用、xがパン、コーヒーがyとか、まあそんな感じです。
つまり、彼は
自分の満足を得るために「他人(社会)の満足」をその計算式に入れると幸せが多く得られますよ。
という、一般的な日本人ならごくごく普通のことを言っているわけなんです。
効用関数は経済学の中でも、個人や家計や企業など、最も小さい単位を扱う「ミクロ経済学」で発達した考え方です。
個人主義の発達した欧米人が長い年月をかけ、徹底して個人の幸福を追求していったら、一周回って社会の幸福と出会ってしまった。
明治の文明開化以来、日本人である私達が半歩遅れで欧米人を追いかけていたら一周回ってなんと自分の後ろ姿と出会ってしまった。
そういうことでしょうか。
自己満足でも偽善でも何でも良いから、
自分の幸せのためには他人の幸せを願う
のが一番良いようです。