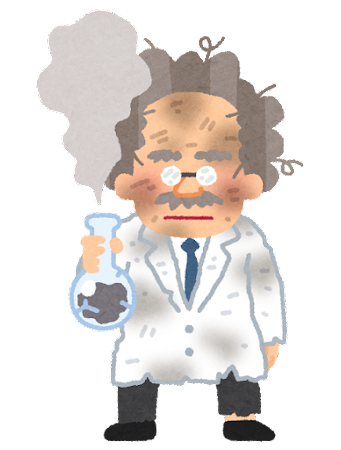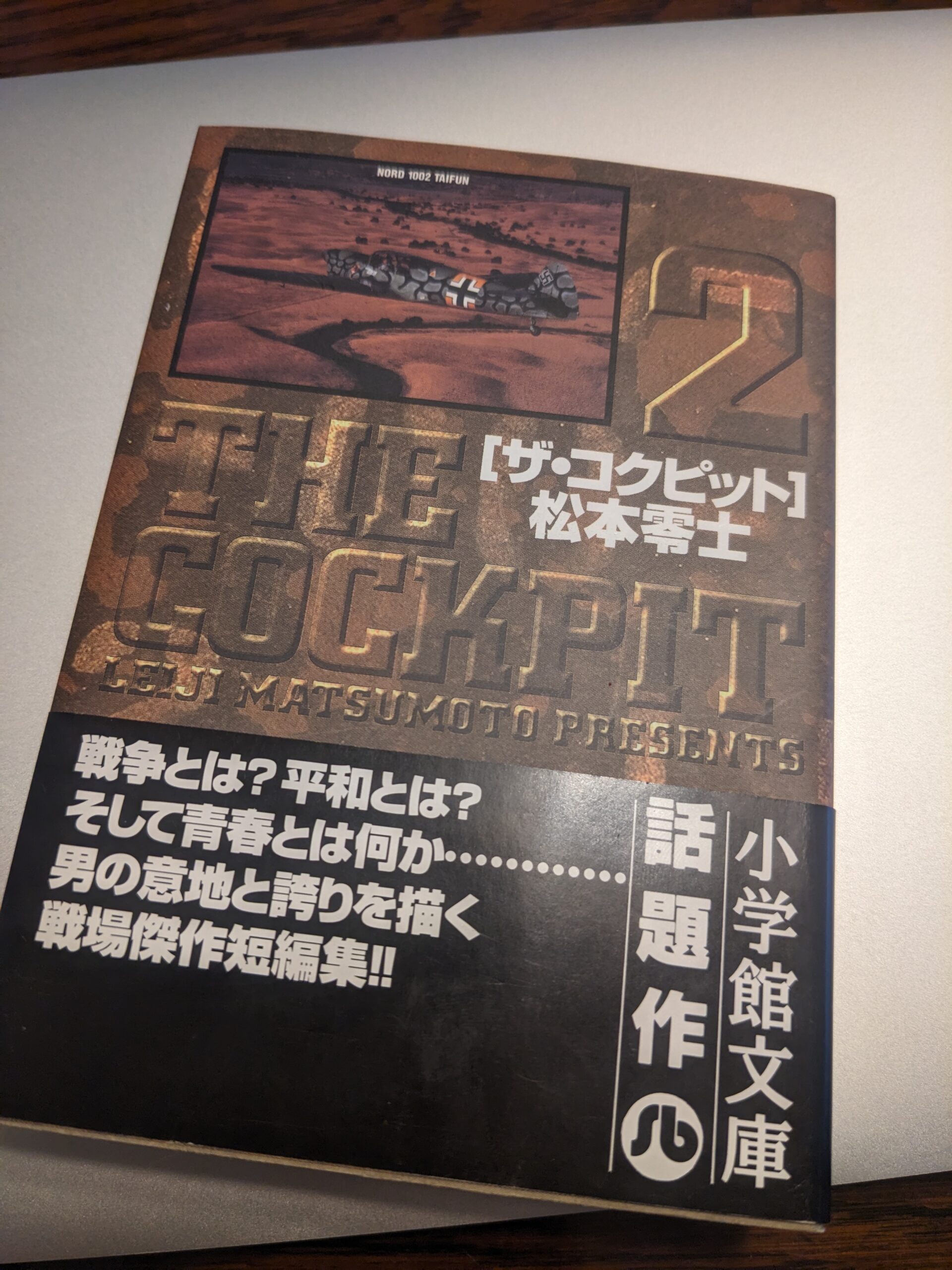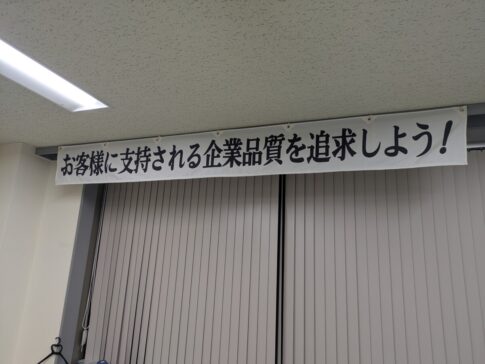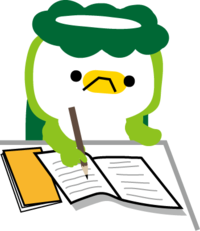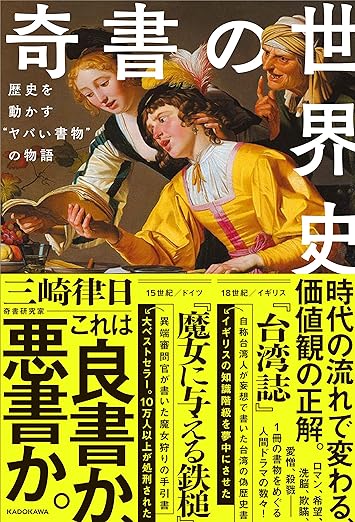エンジェルスの大谷選手すごいですね。
ピッチャーが勝負してくれさえすれば、どんな球でもホームランにできる。
今の調子を見ているとそんな感じさえしてきます。
他にも地元宮城の球団、ゴールデンイーグルスの好調や、ゴルフのマスターズで優勝した同じく宮城出身の松山英樹選手や全米女子を制した笹生優香選手などなど、週末のスポーツ中継はどの試合を見たら良いのか迷うほど。
で、ですね、ちょっと気になったんですけど
「試合」ってなんで「しあい」っていうんでしょうね?
何事も、気になると気になって仕方がない(?)私は早速調べてみました。
Googleってホント便利ですね・・
するともともと「しあい」は「仕合」って書いていたらしいことがわかりました。
つまりは「敵味方に分かれて何かをし合う」というのがその語源だったようです。
でも不思議です。どうして仕合の「仕」の字が「試」に変わっていったんでしょう?
・・ここから先は私の想像なんですが・・・
日本の歴史を紐解くと、武士が殺すか殺されるかの勢いで争っていた戦国時代(この頃の日本人はまさに首狩族だったと思います)がありました。
そこから織田→豊臣→徳川と時代が変わり、関ヶ原の戦いを最後に300年、平和な江戸時代が続きます。
それでも支配階級の武士は戦争するのが本業なので刀や弓の稽古が欠かせません。
そして稽古をすれば「勝負してみたくなる」のが人の常。
とは言っても、武道の場合はほんとに勝負したらどちらかがリアルに死んでしまう。
それで木刀や竹刀などケガをするかもだけど死にはしない道具を使って、「試し」にどっちが強いか勝負してみる。
そのうちに「仕合」が「試しに腕合わせする」という意味の「試合」に変化していったのだ、と超個人的には思うのですがどうでしょう?
時代が変わって、日々競争にさらされるストレスフルな現代で生きることはなかなか大変なことです。
しかしわれわれは事故や病気以外で死ぬことはあまりありません。
少なくとも身の回りに「勝負に負けて死んだ」人を探すことは難しいはずです。
現代を生きるのも日々なかなか大変だけど、毎回の勝負は常に「試しに腕合わせしている」試合である。
「試合」ということは失敗しても死にはしない。
だから毎回の「試合」で「実験」して次に生かしていく。
毎回命がけだと思うと、怖くてなんにもできなくなって、最後はジリ貧になってしまいます。
「一生テスト・一生実験」
だからこんな考えも必要、と思うのですが、皆さんはどう思われます ?
☆ 実は英語にも「テストマッチ(まさに試しに腕合わせする)」という言葉があって、主にラグビーなど、イギリス発祥のスポーツの国際試合で使われるそうです。
もしかして、イギリス人もおんなじようなことを考えているのかもしれませんね。