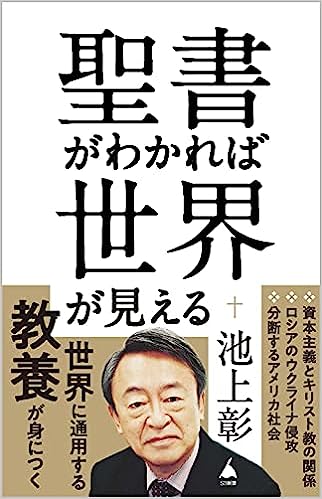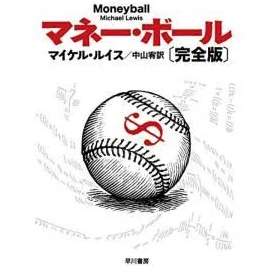私たちエースユナイテッドグループの理念は「未来に貢献」
2017年にホールディングス会社「エースユナイテッド」を作ったときにそう決めました。
事業会社の目的も当然「未来に貢献」です。
主に蓄電池設備を扱うミカド電装商事は「東北のエネルギー・インフラに貢献」
主に小学生向けにプログラミングと英数国を教えるソシオス・イー・パートナーズは「子どもたちの未来に貢献」
エースユナイテッド本体の、経営業務支援(コンサルタント)事業は「中小企業の未来に貢献」
「未来に貢献」の「貢献」の部分については昨年こちらで書きました(https://mikado-denso.com/archives/3291)が今回は「未来」について書かせていただきます。
(未来についてはだいぶ前に書いているような気もしますが、今回は切り口を変えて)
「未来」という言葉に送り仮名をふると
「未だ来てない(いまだきてない)」となります。
つまり、今すぐやってくる何秒後かのことも、ずーっと先のことである例えば5億年先のことも「未来」。
よく「一寸先は闇」なんてことも言いまして、数秒後の未来もどうなるかわからない、といえばそのとおり。
家でボーッとしてたら突然大地震があなたを襲うかもしれませんし、なんの気なしに歩いていたら、突然トラックが突っ込んでくるかもしれません。
そのためか「未来のことなんか考えたってわからない、だから今を一生懸命生きよう!」
とおっしゃる方もいます。
しかし実は我々生き物は、どんな生き物でも必ず先の未来を予測して生きています。
私たちに皮膚があるように、生き物は表皮や甲殻などなんらかの「膜」で、外界と自分を区分していますね。
そしてその区分に囲われた「自分」が少しでも長く現世に存在していられるように、未来を予測して行動します。
例えば私とあなたが細い道ですれ違う場合、お互いに進路を目で確認しあって、ぶつからないように先を予測して右にそれたり左にそれたりしてきれいにすれ違いますね。
あれはお互い(数秒後)の未来を予測しあい(一部のマヌケな例外を除いて)互いにぶつからずにすれ違ってるわけです。
もし現在か過去のことだけ考えている生き物がいれば、たぶん常に正面衝突した後に避けることになるでしょうか。
実はそんな生き物は危険な目に会いやすく生存できないので、繁殖や細胞分裂の機会を失い、子孫やコピーを残せずたちまち絶滅してしまいます(というか存在することもできません)。
逆に言うと「未来を考えたものだけが存続できる」わけで、私達エースユナイテッドが自分たちのことだけでなく「他者の未来に対して貢献」というところまで見据えていけば、自分だけでなく自分の生存するために必要な環境が存続していく、という形になると考えているんです。
そんな中でエースが想定しているのは5〜20年後くらいの未来、その社会に私たちは貢献したい。
なので、今うまく行ってないことでも、未来のために倦(う)まず弛(たゆ)まず、手を変え品を変え、PDCA(計画・実行・検証・改善)しながら未来に進んでいきたいと考えております。
沢田個人としては「過去や現在を気にせず生きることができる」ことが「未来」のために生きる大きなメリットだと考えています。
☆ 「外界と区分されている」「未来を予測した行動をする」これ実は、生物だけでなくあらゆる「システム」の存在条件だそうですよ。