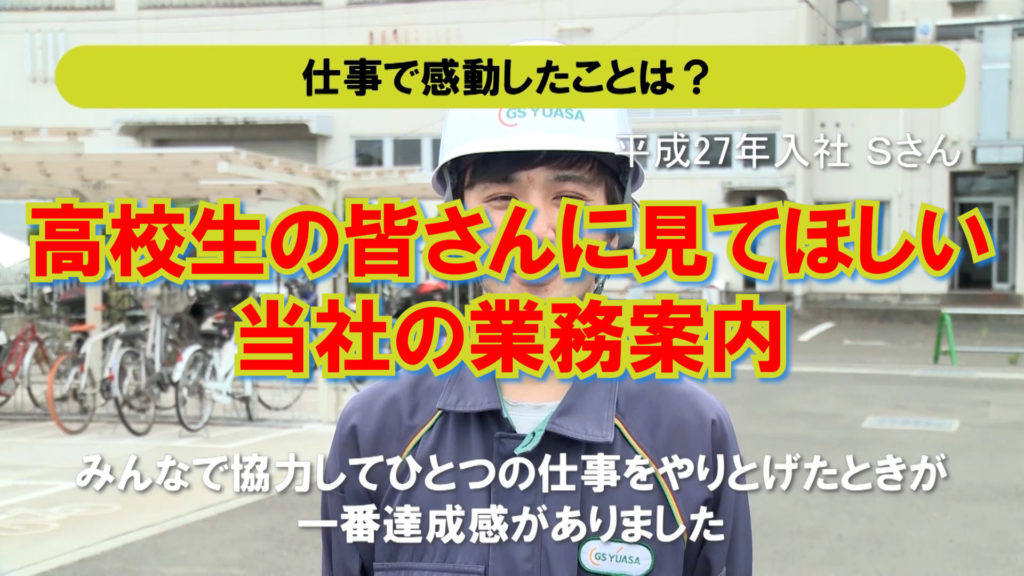核融合は、軽い原子核がくっついて別の原子核になる時にエネルギーを生み出す反応で、いわば太陽が光り続ける仕組みの源でもあります。この力を地球上で安全に使えるようにする、それが「核融合発電」の研究です。
日本では、岐阜県土岐市の核融合化化学研究所が長年の研究成果を基盤とするヘリカル型核融合という方式に取り組んでいます。

プラズマをねじれた磁場で閉じ込める
プラズマとは、気体を非常に高い温度にすることで、原子や分子から電子が離れ、正の電荷を持つイオンと負の電荷を持つ電子が混在した状態の物質のことです。これは「物質の第4の状態」と呼ばれ、太陽、雷、オーロラ、蛍光灯の内部などで見ることができます。
核融合を起こすには、1億度を超える超高温のプラズマを作り、その中で原子核同士を衝突させる必要があります。しかし、プラズマは非常に熱く、容器の壁に触れると一瞬で溶かしてしまいます。そこで研究者たちは、「磁場」という見えない力でプラズマを宙に浮かせる「磁場閉じ込め」という方法を使います。
ヘリカル型核融合では、らせん状に配置した超伝導コイルによって、装置の外側から磁場の形を作り出します。プラズマの中に大電流を流して磁場を作る従来のトカマク型とは違い、ヘリカル型は外側のコイルだけで主要な磁場を形成するため、プラズマを長く安定して閉じ込めやすいとされています。この仕組みによって、現在主流となっているトカマク式では叶わなかった長時間の連続運転(定常運転)を目指せる大きな強みとなりました。
日本の「大型ヘリカル装置(LHD)」が世界をリード

岐阜県土岐市にある大型ヘリカル装置(LHD)は、世界最大級のヘリカル型実験装置です。1998年の運転開始以来、1億2千万度を超える高温プラズマの生成や、54分間の長時間放電など、安定運転に関する多くの成果を積み重ねてきました。
研究では、コンピュータで磁場の形を細かく最適化し、粒子が外に逃げにくい「準対称性」をもつ磁場構造を追求しています。この長年にわたるデータの蓄積と解析が、日本がヘリカル型の研究で世界に先行する技術基盤となっています。
ドイツの核融合実験炉「ヴェンデルシュタイン7-X(W7-X)」も、同じヘリカル系(ステラレータ型)の装置を採用しており、両者は国際的にも連携しながら研究を進めています。どちらも、核融合の“止まりにくい”定常運転をめざすという共通の目標を持っています。
ベンチャー企業「Helical Fusion」の挑戦

近年では、日本発のスタートアップHelical Fusion株式会社も注目を集めています。核融合科学研究所と連携しながら、安定的に運転ができる商用核融合炉を目指して研究開発を進めています。
同社では新しい技術の開発や、装置の小型化と高効率化を進めることで、2030年代の実用化を視野に入れており、初号機の完成は2034年を目標としています。もう近い将来の話ですね。
核融合の方式はヘリカル型とトカマク型がありますが、先に発明された初期のヘリカル型はプラズマの閉じ込め性能が悪かったため、後発のトカマク型に多くの研究者が従事することになりました。しかしコイル技術の進歩などにより、現在では日本がリードしているヘリカル型が見直されています。
ヘリカル核融合は24時間365日の安定した運転が可能であり、次世代クリーンエネルギー源として実用化が期待されています。
(ミカドONLINE 編集部)
参考/引用記事:核融合科学研究所(NIFS)「大型ヘリカル装置(LHD)公式サイト-核融合プラズマのサイエンスとその拡がり , Helical Fusion株式会社 公式サイト-核融合とは?,学術研究基盤LHD計画-学術研究基盤事業大型ヘリカル装置(LHD),MONOist-核融合炉発電の研究を加速、ヘリカル型核融合炉初号機の完成は2034年を目標になど