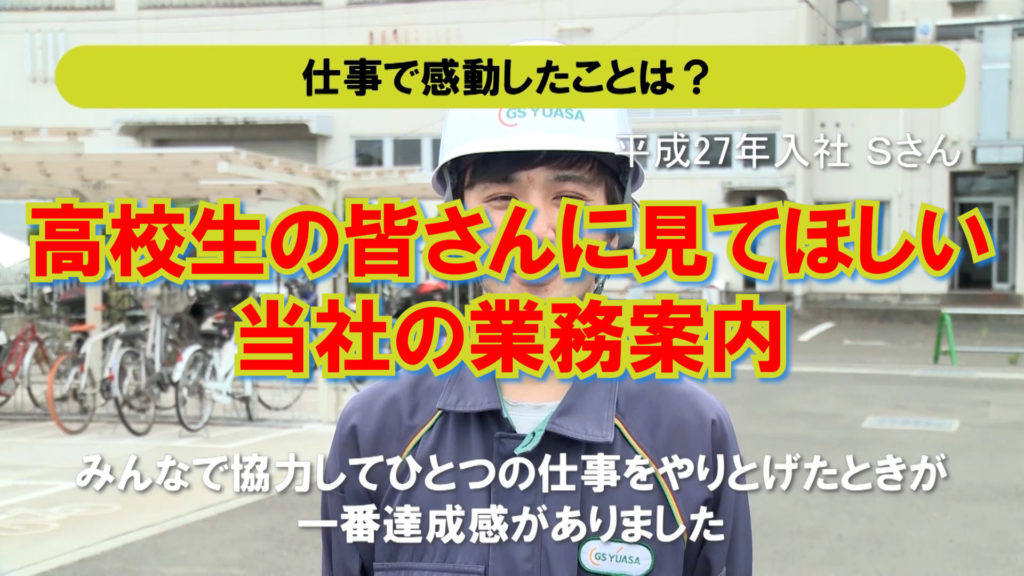「内ポケットに いつも トランジスタ・ラジオ」と歌ったのはRCサクセションの故・忌野清志郎さんですが、トランジスタラジオという呼び名も今はすっかりつかわれなくなり、ラジオと言えば当然のように小さなポータブルラジオを想像する方がほとんどだと思います。
しかしトランジスタが発明される前のラジオは、どんなに頑張ってもラジカセぐらいの大きさで、とても内ポケットに入るようなモノではありませんでした。
その状況を一変させてラジオの概念を大きく変えただけでなく、トランジスタをつかった製品を初めて大成功させて、世界中の人々にトランジスタの実用化をアピールしたのがソニー(当時の社名は東京通信工業)です。
通信マニアがつくったソニーという会社

ソニーは、小さい頃からアマチュア無線やラジオ制作に熱中していた、かつてのラジオ少年たちがつくった通信機器のベンチャー会社でした。そのため、自作機器の性能向上を目的に、常に国の内外から競って新しい技術情報を求める通信マニアの気風がありました。
ソニーの主要陣はある日アメリカの雑誌でトランジスタの発明を知りました。しかし彼らの結論は「つかいものにならない」というものでした。なぜならそのときの発表は最初に発明された点接合型のトランジスタだったから。
創業者の井深大氏は自身の無線経験から、動作が不安定だった鉱石検波器とつくりが似ている点接触型トランジスタに対しては、大きな将来性を抱きませんでした。
しかしその考えが変わったのは、1952年にテープレコーダーの視察を目的に渡米したときでした。当時のソニーはテープレコーダーの生産が軌道に乗って安定を見せ始めていた反面、そのためにかき集めた進取の気性を持つ技術者たちのエネルギーの次なる注ぎ先を模索していたのです。
そこに、現地の友人を通じてニュースが入ってきました。それは、トランジスタを発明したベル研の親会社であるウエスタン・エレクトリック社(以下、WE社)が「希望社には特許を公開してもいい」と言っている、という話でした。
井深氏はその話を聞いたあとに、突然ひらめき「当社には打ってつけ」と思ったそうです。
トランジスタは発明されてから4年経ち、ウィリアム・ショックレーが改良・開発した接合型が発表されていましたが、まだ大きく普及するような商品には使われていませんでした。井深氏は逆にそのことが、社内の技術者魂に火をつけると感じたのかもしれませんね。
当時のソニーは会社を設立してまだ6年しか経っていない無名の会社でした。それがアメリカの大企業から特許権を得ることができたのは、誰の手を借りることなく自力で生産していたテープレコーダーの技術力が評価されたためです。
トランジスタラジオに挑戦しよう

トランジスタはあくまでも電子部品のひとつです。ソニーは通信マニアの会社なので、トランジスタを部品として製造販売するのではく、それを活用して大衆に大きく普及できるような新製品をつくりたいと思っていました。そしてWE社の助言を無視して、ラジオに照準を定めました。
実は、特許契約時のWE社のアドバイスは「補聴器をつくったらどうか?」というものでした。当時のトランジスタは人の耳に聞こえる帯域の周波数しか扱えなかったので、画期的な大発明ではあったものの補聴器ぐらいでしか実用化されていなかったのです。
その段階で日本の小さな無名のベンチャー企業が、トランジスタを製造(当時はこれだけも難しい)するだけでなく、それをつかってさらに難しいラジオを自社で生産するというのですから、「とんでもない、やめておいたほうがいい」というニュアンスが含まれるのは納得できます。

ですが、もう一人の創業者である盛田昭夫氏はそれを聞いて「補聴器では大きなマーケットにならない」とすぐに思いました。ソニーが目指していたのは、需要が見込める新しい商品を世界中に普及させることだったので、決意が揺らぐことはありませんでした。
しかし大きな障害はほかにもありました。当時は外貨の持ち出しが制限されていたため、約2万5000ドル(約900万円)の特許料を支払うためには、通産省から許可を得なければなりませんでしたが、その通産省が許可をおろしてくれませんでした。
「町工場に毛のはえた程度で、難しいトランジスタができるわけがない、そんなことで高額な特許料を支払い、貴重な日本の外貨を使われてはたまらない」というのが通産省の言い分でしたが、事態は時間を経てあっけなく好転。なんと人事異動で通産省の担当者が変わり今度は許可がおりたのです。
けれどそのために失った時間の代償は大きく、その間に、アメリカのリージェンシーという会社がトランジスタラジオをの開発を成功させ、クリスマス商戦の合わせて販売を開始してしまいました。一丸となって「世界初」を目指していたソニー社の、先を越されてしまった落胆は相当なものだったようですが、ここでまたソニーに追い風が吹きました。
世界で初めてトランジスタラジオを製品化したリージェンシー社が約15万台を販売した段階で販売を終えてしまうのです。音質が悪かっただけでなく、トランジスタの歩留まりも悪く、リージェンシー社にトランジスタを供給していたテキサス・インスツルメンツ・セミコンダクター社(以下TI社)が不採算を理由に納入を中止してしまったからです。
成功のカギは最初からラジオを目指したこと

こうした背景下で何度も試作品をつくり、改良に改良を重ね、1955年にソニーのトランジスタラジオの完成品はTR55という名前で初めて市場に投入されました。トランジスタの製造から自社で行ったラジオとしては世界初です。
ソニーはその後も次々と改良を加えた新商品を世に送り出し、それまでコンセントに差して聞く据置型だったラジオのイメージを大きく塗り替えました。特に1958年(昭和33年)に発売したTR-610は世界で50万台も売れて模造品が出るほどの人気でした。
やがてソニーのトランジスタラジオは個人がポケットに入れて持ち運びができるラジオとしてあっという間に普及し、世界が日本の技術力に注目する大きな転機となりました。実際にポケットに入らなくても、アメリカでは販売員がポケットの幅をわざと広くした服を着て「内ポケットに入る」ことをアピールしたというエピソードも残っているようです。

開発には当然、多くの苦労がありました。その後に参入した大手電機メーカーは、アメリカの会社と技術提携を行い、指導を受けて生産を開始しましたが、ソニーの契約は特許の公開のみで技術提携を伴わないものでした。当時のソニーはそこまでが精一杯だったと思われますが、そのため一番参考にしたいトランジスタ製造装置の仕様書など、特許以外の資料は見せてもらえず、工場を見学してもメモや撮影は一切禁止。
研究のためにアメリカに滞在していた同社の岩間和夫氏は、それでもホテルに帰ると自分の記憶だけを頼りに詳細なレポートを書きあげ、膨大な数のエアメールを毎日 日本に送りました。それもこれも世界発のトランジスタラジオをつくりたい!という熱意があったからこそ、ですね。
ちなみにアメリカのリージェンシー社は最初からラジオをつくりたかったわけではなく、トランジスタを製造しているTI社から打診されてラジオの引き受けを受託したそうです。TI社は自社の製品(部品)の認知度を上げるために、目に見える完成品という形に仕上げてくれる会社を探していましたが、どこからも色よい返事を得られず、ようやくたどり着いたのがリージェンシーだったとのこと。
それもそのはず、当時のラジオ(真空管)は、一家に一台の家電製品としてすでに十分浸透していたので、大方の人はこれ以上の普及が見込めない商品と捉えており、まして、技術的な難易度が高く成功するかどうかもわからないトランジスタラジオに対しては、誰もが懐疑的で二の足を踏んでいたのです。
しかしそれをソニーはブルーオーシャンととらえました。一家に一台ではなく、一人に一台の商品をつくれば、市場は飛躍的に広がる、そう踏んだのです。その夢を持って最初から量産化を目指した研究開発であったことが、のちの勝因となりました。
トランジスター開発者のひとりであるブラッティン博士は、のちにアフリカの砂漠を旅したときに、ラクダの背のトランジスタラジオからメロディーが流れてくるのを聞いて、自分たちの発明がここまで来たか、と感激に浸ったそうです。
言うまでもなくトランジスタはやがて電子製品の潮流を大きく変える主要なデバイスとなりました。
(参考)半導体事始め応用編、Sony History、半導体の歴史「20世紀後半 集積回路への発展」 など