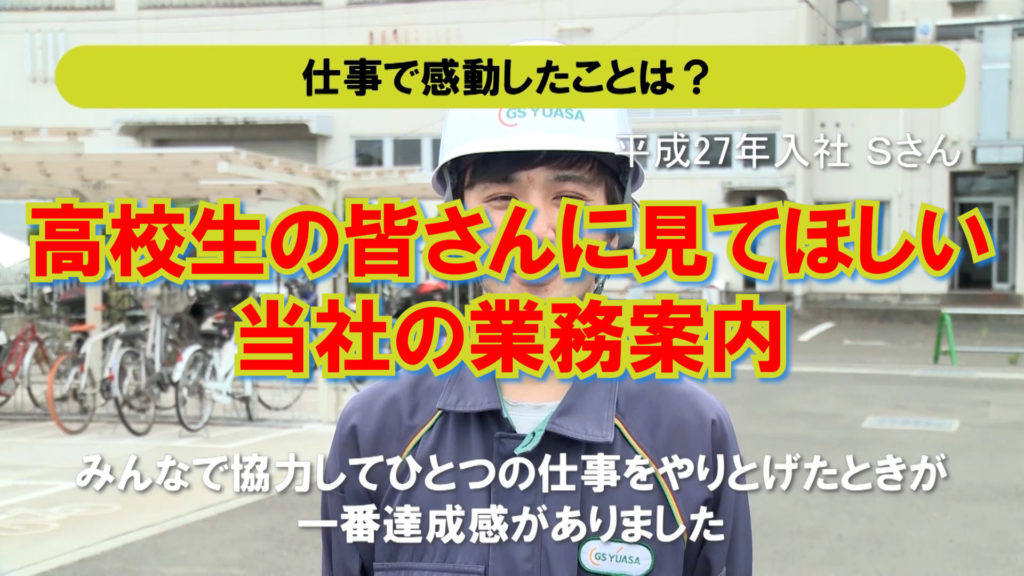地球温暖化の要因となる二酸化炭素(CO2)を、排ガスからどう取り除くか。その答えを探す取り組みが、また一歩進むました。
ジーエス・ユアサコーポレーション(GSユアサ)は北海道大学との共同研究で、電気の力をCO2を使って電離・回収する新技術を開発しました。
火力発電所などの大規模設備にだけでなく、食品工場や中小製造業などにも導入できる可能性を
秘めた、小型・高効率のシステムです。

「pHスイング」でCO₂を取り出す
今回開発された技術の中核は、GSユアサが開発したpHスイング機構にあります。これは電気透析の原理を応用し、電気化学的に溶液の酸性・アルカリ性(pH)を制御することで、CO₂の吸収と放出を切り替える仕組みです。
電気を用いて溶液の状態を変化させることで、CO₂を分離・回収します。この方法は、従来技術と比較して高いエネルギー効率を持つ点が特長とされています。
北海道大学との共同研究により実施された実証では、99%以上の高濃度CO₂ガスの回収に成功しました。これにより、CO₂分離回収における新たな技術的選択肢としての可能性が示されています。
電池技術を応用実証機が稼働、次のスケールへ
この技術を適用した小型の実証機が2025年7月から稼働を開始しました。
実証機では、1日あたり最大1kg規模のCO₂を処理できるレベルまで性能が高められています。
今後はこの成果を踏まえ、1日1トン規模のCO₂処理を目指した装置へのスケールアップが計画されています。実証段階から実用化を見据えた開発フェーズへと進むことで、より大きな排出源への適用も視野に入っています。
より大きなな排出源への適用も視野に入っています。
小さな装置で広がる可能性
今回の技術は、小型の実証機で運用可能で、環境負荷の低減が期待される点が特長です。
そのため、食品工場や醸造所など、中小規模の排出源への導入拡大が想定されています。
また、回収したCO₂は、地下に貯留するだけでなく、エネルギー源や化学品原料などへの利用も想定されています。本技術は、GSユアサと北海道大学の共同研究により開発が進められています。
(ミカドONLINE 編集部)
参考/引用記事:株式会社GSユアサ公式ニュースリリース「GSユアサと北海道大学が共同研究で革新的なCO₂分離回収技術を開発 ~高エネルギー効率・99%以上の高濃度CO₂ガス回収を実現~」,日本経済新聞「GSユアサ、排ガスからCO₂回収する装置開発 中小工場向け30年度発売」