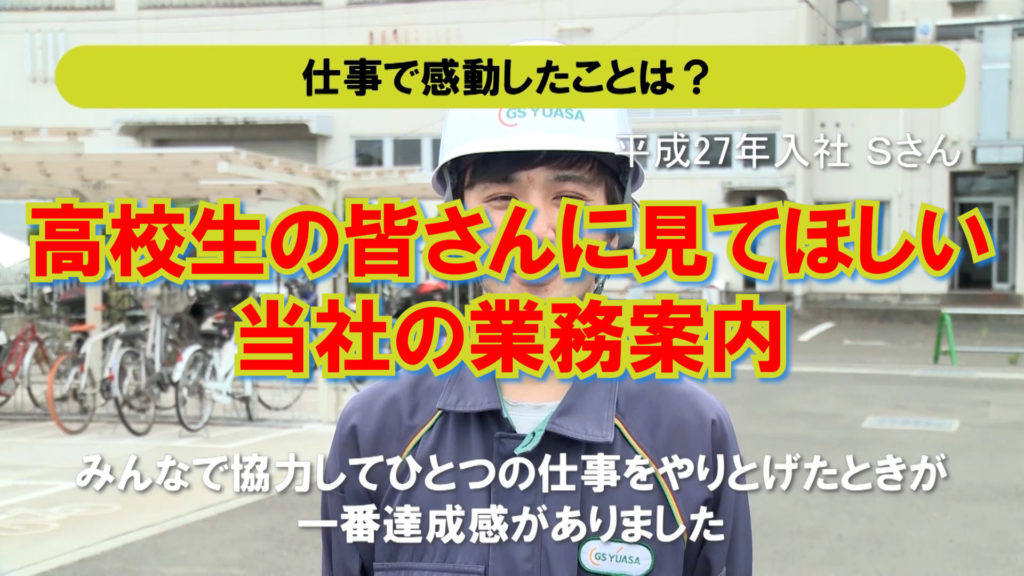(「電波の歴史」全記事はこちら)

ラジオからテレビへ
前回はAM変調技術をつかって、世界で初めて(モールス信号ではない)人の声や楽器演奏を無線で放送(1906年/明治39年)したフェッセデンについてお伝えしました。音声を伝送する技術はその後、ラジオの商業放送へと形を変えていきました。アメリカでは1920年にペンシルベニア州ピッツバーグのKDKA局が世界最初の公共放送が開始し、日本でも1925年(大正14年)日本初のラジオ放送が社団法人東京放送局(JOAK:現NHK東京放送局)によって発信されました。
一方、当時の先端技術の研究者の中には、音声だけでなく映像も伝送できないか?と考える人達が現れ始めました。その動きはやがて、テレビの開発へとつながっていきました。
それまではトンツーのモールス信号しか送受信できなかった電波を通じて、人の声や楽器の音色まで再現できるラジオ放送技術は確立しつつあったものの、その電波にいったいどうやって動きのある映像を乗せていくのか?
そこで最初に発明されたのが、テレバイザーと呼ばれる機械式テレビでした。
機械式テレビジョンとは?
テレビそのものが”機械”なので、ここで改めて「機械式テレビ」と言われると少々混乱してしまいますが、「機械式テレビジョン」とは、映像の取り込みも再現も、回転するモーターをつかって物理的に行うテレビのことです。
考案したのはイギリスの電気技術者で発明家のジョン・ロジー・ベアードです。ベアードはすでに発明されていたニプコー円盤というアナログの画像分解装置をつかって、静止画をパラパラ漫画のように連続して送ることで、動く映像の伝送に成功しました。
これはらせん状に穴をあけた円盤(ニプコー円盤)を回転させることによって動きのある映像を静止画に分断して光の強弱を電気信号に変換するものでした。
ベアードが考案した仕組みはBBCに採用され、テレバイザーと呼ばれる受信機もある程度出回りましたが、画像の品質を上げるためには物理的な限界があり、やがて電子式テレビに置き換わってしまいました。
走査線のアイデアは畑の畝(うね)から

電子式のテレビを発明したのは米国のフィロ・ファーンズワースです。ファーンズワースは1906年(明治39年)に電気のないユタ州の田舎町で小作農家の息子として生まれましたが、引っ越し先の家に電灯が引かれていたことに興奮し、電気に強い興味を持ちました。
そして手づくりモーターを自作して家の洗濯機を電動にしてしまったり、雑誌の発明コンコールで賞金をもらうなど少年の頃から物理的な才能を発揮し始めました。
ファーンズワースはある日、馬がジャガイモ畑を行き来しながら畝(うね)をつくっていく軌跡を見て、現在のテレビにつながる走査線のアイデアがひらめきました。
画像を線状に分解してそれを紐のようにつなげた電気信号を無線で伝送し、受信側で再構成すれば離れた場所でも再現できるのではないか?
「映像が空気を伝わっていったらどんなに素晴らしいことだろう」
その夢に取りつかれたファーンズワースは、高校生のとき科学の教師に熱くアイデアを語り、自分が考えた仕組みを黒板に書きました。その秀逸さを知った教師は質問に答えながらファーンズワースを励まし、頑張って実現させるように伝えました。
テレビに目を付けたRCA社
ファーンズワースはその後、父の死で大学をやめなければならなくなり、いくつかの仕事を転々としながらも研究を続けました。やがてスポンサーが現れたため自分の研究所を持つことができ、ついに映像を時系列で電気信号に変換できる初期の撮像管(イメージディセクタ)を考案してテレビの原型をつくりました。
そして改良を重ねながら1927年(昭和2年)に特許を取得し翌年には公開実験にも成功して、機械要素のない完全な電子式テレビシステムを完成させましたが、ここに大きな問題が立ちはだかりました。特許の優先権を主張したRCA社との法廷闘争に巻き込まれてしまったのです。
当時はラジオの商業放送もすでに始まり受信機もある程度普及していましたが、ラジオ放送各社は次世代の新しい技術として映像送信に注目し、それぞれが独自にテレビ放送の実験を試みていました。
 RCA社は元々の社名をRadio Corporation of America(アメリカ・ラジオ会社)とする巨大企業ですが、その前身はアメリカン・マルコニー社です。前々回ご紹介したあのマルコニーのアメリカ現地法人がゼネラル・エレクトリック、AT&T、ウェスティングハウスに買収されてできた会社です。
RCA社は元々の社名をRadio Corporation of America(アメリカ・ラジオ会社)とする巨大企業ですが、その前身はアメリカン・マルコニー社です。前々回ご紹介したあのマルコニーのアメリカ現地法人がゼネラル・エレクトリック、AT&T、ウェスティングハウスに買収されてできた会社です。
そのためRCA社はマルコニー社が持つ特許やほかのラジオ開発者の特許をほとんど押さえており、ラジオを製造するにはまずRCA社に多額の特許料を支払わなければ、一切の参入ができない状態でした。後年の日本のラジオメーカー各社もRCA社には多くの特許料を払っており、RCA社は特許料で莫大な利益を得て巨大化した会社だったのです。

そのRCA社が保持していた特許もやがて失効する時期がやってきます。同社はそれを見越して次なる覇権を得るためテレビに目を付けました。亡命してアメリカに渡ってきたロシアの科学者ツヴォルキンがテレビを研究していたことを知るとすぐに彼を採用して電子式テレビを開発させました。
ちなみにこのときのRCAの社長もまたロシア系アメリカ人で、のちにNBCをつくったサーノフという人です。サーノフはRCAの前身のマルコーニ社に給仕として入社し、その後無線技士を経て社長にまで上り詰めた人物ですが、あのタイタニック号のSOSを最初に受信した人らしいです。発見者のヘルツが「何の役にも立たない」と言った電波は、こうして利益を生み出す一大ビジネスに変貌を遂げていきました。
判決の決め手は恩師のスケッチ

ツヴォルキンがつくったテレビは送信にも受信にもブラウン管(陰極線管)をつかうものでしたが、その時点では送信側に独自の撮像管を採用したファーンズワースのシステムのほうが圧倒的に優れていました。
身分を偽り会社の命を受けてファーンズワースのテレビを見に来たツヴォルキンは一研究者としてその優秀性に感銘し、それを会社に報告すると共に開発チームには複製を指示しました。
報告を受けたRCA社はすぐにファーンズワースの特許を10万ドルで買い取ろうとしましたがファーンズワースはこれを拒否。するとRCA社は自分達の方が先にテレビを開発していると主張して、特許の優先権を法廷に持ち込みファーンズワースに特許料を支払うよう訴えました。
闘争は長引き、巨大企業を相手に戦うことになったファーンズワースは、裁判のための資金集めに奔走せざるを得なくなり、せっかくの画期的な発明も結論が出るまでは実用化に着手できなくなりました。

しかし苦節の末、ファーンズワースはついに1935年(昭和10年)の判決で勝利を勝ち取りました。その大きな決め手となったのがファーンズワースの高校時代の恩師 ジャスティン・トルーマンの証言でした。彼はファーンズワースが14歳のときに黒板に描いた図を再現したスケッチを提出したのです。これにより法廷闘争はようやく決着が付き、ファーンズワースが在籍していたフィルコ社は中小企業でありながら、あのRCA社が初めて外部に特許料を支払った会社になりました。
月面放送に自らの価値を見出す

ファーンズワースは1971年(昭和46年)に64歳で亡くなりましたが、経済的には決して豊かな人生ではありませんでした。ファーンズワースが電子式テレビを発明して特許を取得したのは21歳の頃と思われますが、そのことにより、彼は以後のほとんどの時間とお金とエネルギーを、大企業との抗戦に費やすことになってしまいました。
主とする裁判には勝っても、その後の数年間は残っている他の訴訟があり、それらが終結してようやく開発に没頭できると思った矢先に今度は第二次世界大戦が勃発し、その間に特許も失効してしまいました。のちにファーンズワースがつくった会社は資金難に陥り、ファーンズワースは全財産を換金し生命保険も解約して保全に努めましたが、事態は好転することなく会社は解散しました。
そんなファーンズワースが自分が歩いてきた道を肯定できたのは、アポロ11号が月面に降り立ったテレビ中継を見たときでした。彼はそのとき初めて、自分の発明に価値があったと認めることができたのです。ファーンズワースの妻によれば、それまでは確信が持てなかったそうなので、ファーンズワースの一生は悩み多きものだったのでしょう。
テレビの父とされながらも、大企業の発信力の陰に埋もれていたファーンズワースは近年再評価され、2003年にはエミー賞の技術部門としてファーンズワース賞が創設されました。その2016年の受賞者はNHK、2017年の受賞者はSONYでした。
テレビの開発者としては日本の高柳健次郎博士も著名ですが、高柳博士の考案した最初のテレビは送信側にニプコー円盤をつかった半機械式だったことや、慎重を期して発明の1年後(1927年)に特許を出願したことなどが影響して、いち早く先手を打ったRCAのツヴォルキンや送受信の両方を電子化したファーンズワースにはいま一歩及びませんでした。
けれど、偶然にもまったく同じ時期にそれぞれが別個に走査線の概念を考案していたことは世界的に評価されており、海外の技術系サイトの年表にはファーンズワース、ツヴォルキンと肩を並べて必ず高柳博士の名前が記載されていることを最後に補足しておきたいと思います。
▲ゲストの秘密を当てるアメリカのクイズ番組に出演したファーンズワース。誰も正解できないことから、当時の彼はテレビの開発者としては無名であったことが伺えます。
(つづく)