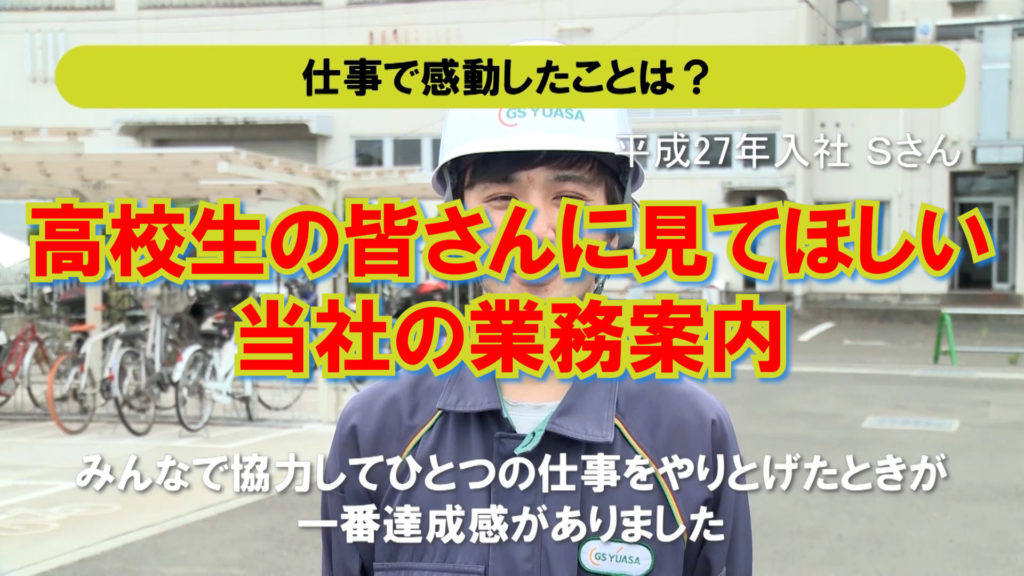人間による温室効果ガスの排出量のうち約25%が農業に由来すると言われおり、アメリカのワイン農家ではではカーボンファーミングと呼ばれる農法が増えています。効果を疑問視する声もあるのに導入が進んでいるのはなぜ?
人間による温室効果ガスの排出量のうち約25%が農業に由来すると言われおり、アメリカのワイン農家ではではカーボンファーミングと呼ばれる農法が増えています。効果を疑問視する声もあるのに導入が進んでいるのはなぜ?
カーボンファーミングとは?

地球温暖化対策やCO2、メタンなどの温室効果ガス削減という言葉を聞くと、誰もが真っ先に産業分野でつかわれる化石燃料を思い浮かべると思います。ところが実は、人間による温室効果ガスの排出量のうち約25%が農業に由来するそうです。
牛のげっぷから出るメタンは以前から話題になっていましたが、もっと大きな問題は土を耕すこと。つまり土を耕すことで土中に閉じ込められていた炭素が大気中に放出されしまい、その量がどうやら半端ではないらしいのです。
 炭素は本来、生物の生態系を通じて地球を循環している物資です。光合成で育った植物の枯死や、植物を食べて育った動物の糞尿や死骸によって土壌に移動し、それを微生物が分解して大気中に放出したものが新たな植物の養分になったりしています。
炭素は本来、生物の生態系を通じて地球を循環している物資です。光合成で育った植物の枯死や、植物を食べて育った動物の糞尿や死骸によって土壌に移動し、それを微生物が分解して大気中に放出したものが新たな植物の養分になったりしています。
Wikipedia(英語版)によれば ”世界中の土壌に保存されている炭素は2,700 Gt” で、これは ”現在の大気中の炭素の約3倍、現在の年間化石燃料排出量の240倍” なのだそうです。ゆえにその増減は地球温暖化に大きな影響を及ぼすとされています。
そのため炭素を土中に閉じ込めて貯留しておくには、土を耕さない方が効果的であるというアイデアが提唱され始め、他の様々な手法と組み合わせながら、グリーンな農法として徐々に確立してきました。それがカーボンファーミングです。
一例としては以下のような手法が挙げられます。
- 耕作(耕起)の頻度を下げる
- 土地の表面を堆肥などの有機物質で覆う
- 緑肥作物を植えて土壌を保護する
- 排水溝をなくす代わりに樹木を育てる
また、放牧の場合は、長期間広範囲に放牧すると草原が破壊されるため、群れはいくつかの囲いをローテーションで毎日移動させ、順繰りに土地を休ませて草地を復帰させます。
それらには(もちろん)電力はなるべく再生エネルギーを使うとか、(もちろん)化石燃料を原料とする化学肥料は使わないなども含まれます。
カーボン・ファーミングに詳しいカリフォルニア大学バークレー校のウェンディ・シルバー教授によれば、多めに見積もった場合、この農法を世界規模で実施すれば、世界の年間CO2排出量を100%回収・貯留できる試算も可能だそうです。
賛否両論でもカーボンファーミングがワイン農家に支持されている理由

今までは土中の微生物を活性化させたり植物の根張りをよくする目的で土が耕されてきました。一方、不耕起栽培で土中の炭素が増えると土壌自体が肥沃になります。また耕さないことで土が乾燥せずに湿気を保つので干ばつ対策にもなり、有機肥料をつかうことで安全で健康的な土壌がつくられます。土壌を最適な状態に保つことは、農地の生産性を上げると共に、雨や風による土壌侵食にも強い土地になるそうです。
従来の農業慣習にはないこの農法には優れた利点が数多くあります。けれどその一方で効果を疑問視する声があるのも現状です。そのポイントは「耕さないこと」ではありません。
専門家が掲げる問題点は以下の通りです。
土壌に蓄積される炭素の量は季節変動が大きいことから、正確な計測が非常に難しい
実際に効果を示す明確な数字が得られていない
さまざまな土壌タイプや深さ、地形、作物の種類、気候条件、期間において、どの農法がどの程度機能するかについては今もって不確実
農法として持続可能かどうかも不明
カーボン・ファーミングが食糧生産量を損なうことなく、世界中の農場で長期間にわたって大規模に実施可能かどうかは不明
これらを見ると、現状で確実なものは何一つなく、期待値だけが一人歩きしている感もあります。
けれどアメリカのカリフォルニア州のワイン用のブドウを栽培する農家の間では、意外にもこの農法への指示が広がりつつあります。それはワイン農家にとって地球温暖化は切羽詰まった死活問題だからです。
カリフォルニア州最大のワイン生産地はナパバレーという地区ですが、その地域を代表するブドウがカべルネ・ソービニヨンという高級品種です。従来はこの品種にとってカリフォルニア州北部の気候は最適でしたが、それが気候の温暖化により、高級品種に適した地域は2039年までに半減する見込みとなっているのです。ナパのワイン農園が自分たちの生活を守り、地球温暖化防止にも貢献するために乗り出し対策が、カーボンファーミングだったのです。
数値がどうの、評価がどうのという話ではなく、とにかくできるものから手あたり次第やっていこうという意思も感じたりします。
ビジネス化するカーボン取引

カーボンファーミングが広まるきっかけになったのは、2011年にオーストラリアが実施したキャップアンドトレードプログラムです。これは温室効果ガスの排出権を取引できる仕組みのことで、簡単に言えば政府が決めた目標を上回る削減値を達成できた事業者は、余った分の削減量を他の事業者に売ることができる制度です。
削減目標に届かない事業者は、他の事業者から余剰削減量を購入することで、数字の上では目標を達成でき、かつ温暖化防止に関わる様々な市場を経済的に活性化させる目的も含まれています。
カーボンファーミングはその過程で農園の新たな収入の手段として急浮上してきたようです。しかし極端な言い方をすれば、資金のある事業者は余剰の削減量を購入するだけで目標を達成できてしまうことや、基準や測定方法が未確立で本当に温室効果ガスが削減されているのかわからない施策に対しても、クレジットが発行されてしまうケースなどもあり、これはこれで論議を呼んでいるようです。
米国の連邦議会では現在、カーボン・ファーミングを排出量取引制度に組み込むための法整備が進められています。法制化が実現すれば、農業生産者は温室効果ガスの削減に寄与することで報酬を得られるようになります。
カーボンファーミングが注目されている背景には、そういった事情が絡んでいることも確かです。世界はすでにカーボン(炭素)が商取引の素材として扱われ、様々な人々の様々な思惑が絡み合う複雑な状況になっているようです。
(ミカドONLINE編集部)
出典/参考記事: ワイン農園に支持されるカーボン・ファーミングの可能性 など