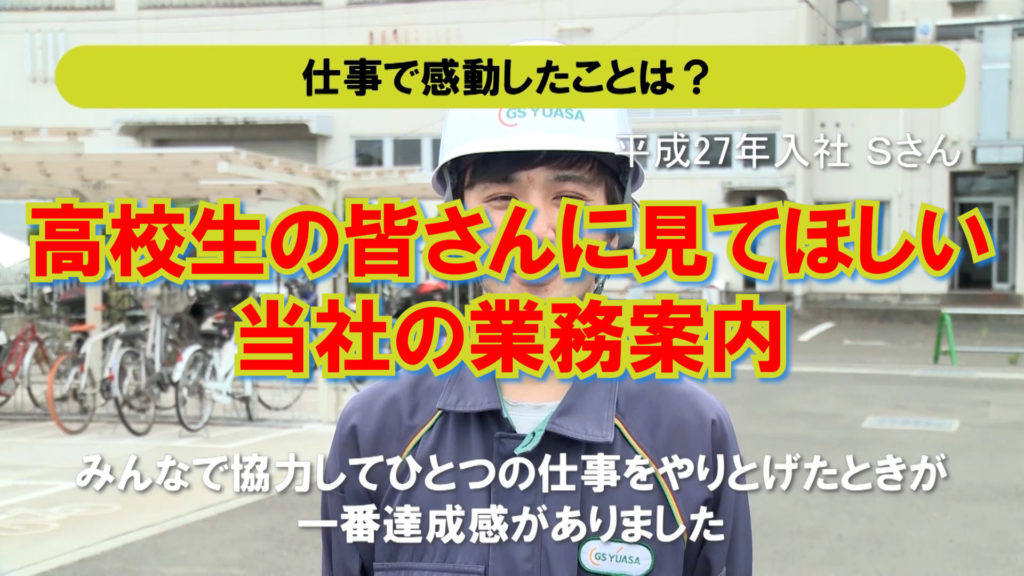今回は当社の会長が「北海道を旅行したときに海辺に群生する風景が印象的だった」と話すハマナスを取り上げたいと思います。歌の「知床旅情」でも有名な花ですよね。
ハマナスはハマナシが東北弁で訛ったという説

ハマナスは、バラ科バラ属の落葉低木で、北海道を中心に、本州の太平洋側では茨城県まで、日本海側では鳥取県あたりまでの海岸に自生しています。学名は Rosa rugosa ですが、これはラテン語で「しわくちゃのバラ」という意味になります。
ハマナスは6月から8月にかけて、鮮やかな紅紫色(まれに白)の花を咲かせ、甘くさわやかな香りを放ちます。花の直径は7〜9cmと大きめで、見た目も香りもバラそのものですが、潮風や砂地に強く、過酷な環境にも耐えるたくましさが特徴です。
名前の由来は「浜に生えるナシのような実(浜梨=ハマナシ)」から来てるという説が有力です。それが東北や北海道で訛って「ハマナス」になったとのこと。これには諸説ありますが、この考えは植物学者の牧野富太郎博士が提唱したものです。
調べてみると昔は「ハマナシ」と呼んでいる人もそれなりに居たようで、今も「ハマナシ」という名前を採用している植物図鑑や公園があるそうです。けれど「知床の岬にハマナスの咲くころ~♪」と歌う「知床旅情」の全国的なヒットで呼び方が統一されてしまったのかもしれませんね。
海辺で咲くバラの仲間というだけあって、寒さや塩分にも強く、北海道だけでなく、シベリアやカムチャッカ半島などの厳しい環境でも元気に育ちます。まさに“耐えて咲くバラ”。日本最北のバラと呼ばれるのも納得です。
花も実もあるストロング&ビューティ

バラ科の植物の実をローズヒップと言いますが、ハマナスのローズヒップはビタミンCの含有量が非常に多く、なんとレモンの20倍とも言われています。このローズヒップは昔から風邪予防や美容に良いとされ、ジャムやハーブティー、さらには化粧品の原料にも使われています。
また、ハマナスは北海道の「道の花」としても親しまれており、地域のシンボルにもなっています。文学の世界にもたびたび登場し、石川啄木は「浜茄子の 実の赤きかな」と詠みました。さらに、童話作家の宮沢賢治も「オホーツク挽歌」という詩の中で取り上げており、色鮮やかな花の美しさが文学者を惹きつけるのかも。
現代では園芸品種としても人気があり、耐寒性と耐病性に優れた植物として庭づくりにも活用されているハマナスは、美しいだけでなく栄養が豊富で潮風にも強く、まさに「花も実もある」海辺のストロング&ビューティと言えるでしょう。
(ミカドONLINE編集部)
参考/引用 Aboc – アボック社 -ハマナスとハマナシ、二つの和名を巡って など