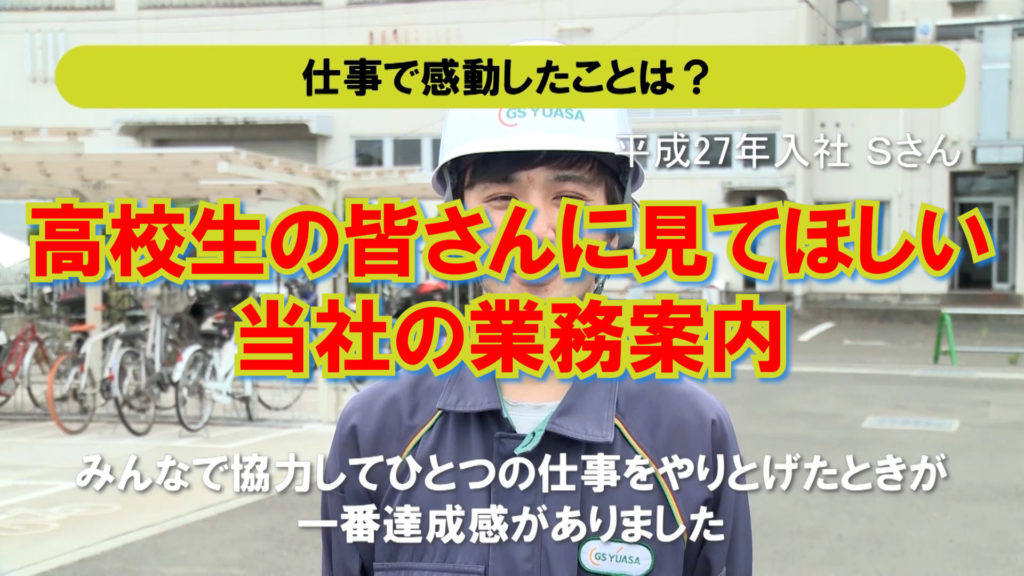スベリヒユは、日本全国の道端や畑、庭先などで見かける地を這うように広がる野草です。普段は雑草扱いされていますが、実は驚くべき生命力と、多様な魅力を秘めた植物なんです。
乾燥にも踏みつけにも負けない驚異のサバイバル力

スベリヒユは、日本全国の畑地や道ばたなど、日当たりが良く、乾燥した場所に生育する一年草です。市街地の植え込みはもちろん、コンクリートやアスファルトの間隙などにも生育します。世界中の温帯~熱帯地域に分布しており、日本には農耕とともに、古い時代に入ってきた「史前帰化植物」のひとつであるとされます。
夏の炎天下、他の雑草が枯れ果ててしまうような環境でも、スベリヒユだけが元気に地を這っているのを見たことがあると思います。これは雑草界の生存王と呼ばれるほどの強靭な生命力を持っているからです。
スベリヒユが乾燥に強いのはCAM型光合成という特殊な光合成のお陰です。
通常の植物は太陽が昇ると空気中の二酸化炭素を取り込んで光合成を行いますが、CAM型光合成の植物は夜間に二酸化炭素を取り入れて、リンゴ酸などの有機物の形でいったん葉の内部に貯蔵します。
そして通常の光合成は涼しい午前中のうちに終わらせて、気温が上がる午後からは夜間に貯蔵しておいたリンゴ酸を二酸化炭素に戻して光合成を行います。それによって気孔が開く時間を最小限にとどめ、水分が外に逃げていくのを防いでいるのです。
CAM型光合成はサボテンやアロエなど、乾燥地の多肉植物によくみられる光合成の方式ですが、これは水分が極端に少ない環境に適応してきた結果で、ほかの観葉植物・多肉植物と比べて1/10の水分量で生きていけるそうです。
またスベリヒユは効率よくハイスピードで光合成ができる「C4植物」という部類に属しており、植物全体の中では少数派(1割以下)ながら、少ない資源でも生きていける能力があり、再生能力も高いため、日当たりがよければ荒地でも砂漠でも、そして都会で踏みつけられても生き延びていけるツワモノなのです。
実はスーパーフード!? ~雑草だけど栄養満点の健康食材~

スベリヒユを漢字で書くと「滑莧」です。「莧(ひゆ)」の字は、ヒユ科の植物のことを指す漢字であり、食べるとぬめり(滑り)があるヒユ、ということを意味しています。ヒユ科にはホウレンソウなどをはじめとして、野菜として栽培されたり、山菜として利用される植物が多くあります。
実はスベリヒユも食べることができるんです。
私も今回初めて知りましたが、地中海地方ではサラダにして食べ、中国では馬歯莧と呼ばれて薬草として親しまれ、沖縄ではニンブトゥカー(念仏鉦)と呼ばれ重宝される、などなど各地で食用とされる優秀な野草らしいのです。
お味も、茎や葉をさっと茹でて、和え物、お浸し、油炒めなどにすると、ぬめりとわずかな酸味があってなかなか美味とのこと。
探してみるとスベリヒユを絶賛しているブログを見つけたのでぜひ以下をご覧ください。様々な調理方法を嬉々として紹介しているその内容に個人的には軽い衝撃?を受けました。そんなに美味しいのでしょうか・・・?
(参考)スベリヒユがウマすぎるのでたくさん料理してみた | 東京でとって食べる生活
しかもさらに調べてみると、スベリヒユはビタミンCやβカロテン、カルシウム、マグネシウムなどのミネラルも豊富で、動脈硬化の予防や脳の健康維持に役立つとされるオメガ3脂肪酸も多く含んでいるので、まさに栄養満点のスーパーフードなのだそうです。
ここまで書いても、スベリヒユを食べてみたいとはあまり思わない私ですが、それも食わず嫌いの感情なのしら・・・。旅館や民宿で何も知らずに出来上がったものをいただいて「美味しい!」と思ったときに”やる気”のスイッチが入るのかもしれませんね。
(ミカドONLINE編集部)
出典/参考記事: 重井薬用植物園 | おかやまの植物事典 乾燥や熱にめっぽう強いCAM植物とは?元気な多肉植物を育てるコツをご紹介!|midoritoridori C4植物のきほん など