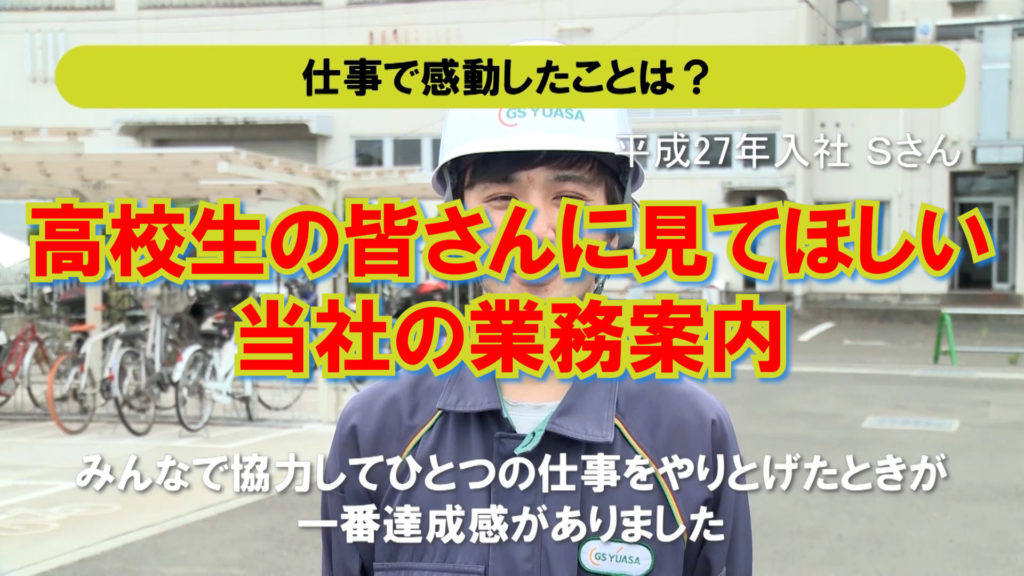秋春になると爽やかな香りをはなつよもぎですが、実は秋にはこっそり小さな花を咲かせる植物でもあります。団子や草餅など食用としても親しまれ、どこか和を象徴するような草ですが、花の姿は意外と知られていません。この記事を書いている私も、なかなかどんなものか思い浮かびません。今日はそんなよもぎの花に触れてみます。
1.よもぎの花ってどんな花?
よもぎの花は、夏の終わりから秋にかけて咲きます。といっても、全く派手な花ではありません。黄緑色の粒々とした小さな花が穂のように並びます。見た目こそ地味ですが、地下茎から他の植物の初芽を抑制する物質を分泌させているのだそう。少し毒気がありますね。

普段目にするのは香りの良い若葉ばかりなので、よもぎに花が咲くのを初めて知ったという声も多い、不思議な花です。
2.実はとてもしたたかな雑草
よもぎは先述したとおり、地下茎(地中に伸ばす茎)でどんどん広がるため、一度根付くと簡単には抜けません。花が地味なのは、派手に虫を呼ばなくても、風で花粉が飛ぶ風まかせの方法で仲間を増やせるから。人の暮らしのそばにしぶとく生えている理由は、そんな強さにあります。
3.花より馴染みある葉
よもぎというと皆さん葉を思い浮かべますよね。葉にも人々の暮らしに寄り添う深い歴史があります。
まずよもぎの葉は、おまじないの草としての役割を果たしてきました。昔から厄除けの象徴とされ、端午の節句ではショウブと一緒に軒先に吊るしたり、よもぎ湯に使ったりして邪気を払うという風習がありました。
その香りの強さとしぶとい生命力も悪いものを払う力だと例えられていたのです。

何度も登場している香りについてですが、料理やお菓子に使われるだけでなく、昔の人は虫除けや傷の手当にも利用していました。乾燥させて使う「もぐさ」はお灸の材料として今でも使われています。静かに咲く花とは対照的に、暮らしに深く根差した万能草でした。
普段は葉ばかりが注目されるよもぎですが、秋にはひっそりと小さな花を咲かせています。
目立たない花の裏には、確かな生命力と古くから人々の暮らしを支えてきた深い歴史がありました。道端でふわりとかおるよもぎに出会ったら静かな花のことも思い出してみてください。
(ミカドONLINE編集部)
参考/引用 公益社団法人日本薬学会 花(よもぎ),岡山理科大学 ヨモギなど