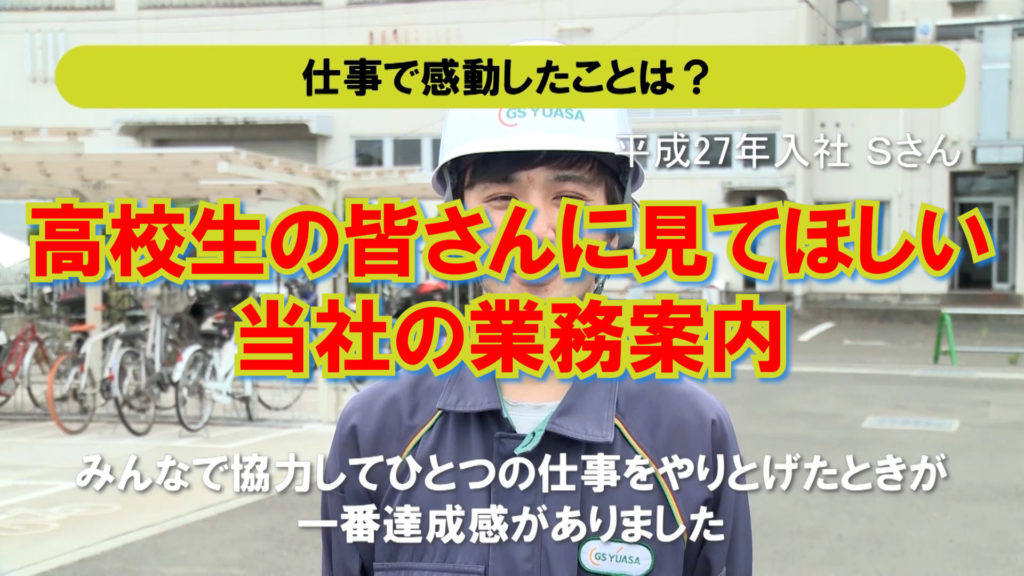製造時のCO2排出量を大幅に抑えた鉄をグリーンスチールと言います。製鉄は大量の石炭をつかうため、世界的に見ても有数のCO2排出産業です。そのためグリーンスチールの量産化と普及が望まれますが、新しい方式の高額なコストや設備の建設に巨額の資金が必要になるため、実際には一部の欧州企業が供給を始めたばかりです。今回はグリーンスチールを取り巻く日本と欧州の事情をご紹介します。

グリーンスチールは環境にやさしい鉄
先月(2025.6月)、北九州市の地ビール会社「門司港レトロビール」の缶ビールの素材に、日本製鉄株式会社のグリーンスチールが採用されたことが発表されました。
日本製鉄 日本製鉄のグリーンスチール「NSCarbolex Neutral」が門司港レトロビール株式会社のスチール缶ビールに採用
グリーンスチールとは、鉄をつくるときに出る二酸化炭素(CO₂)を大幅に減らした環境にやさしい鉄のことです。
アルミ缶からの切り替えは、日本製鉄八幡製鉄所を有する北九州市が鉄の町であることに加え、環境意識の高い欧米からの観光客にもアピールしたい狙いがあるのかもしれません。
近年は以下のように脱炭素の方法・由来・手段などをわかりやすく色の名前で区別するケースが増えてきました。
✅ グリーン(Green)
- 由来:再生可能エネルギー(太陽光・風力など)や水素
- 例:グリーンスチール、グリーン水素、グリーンアルミ
- 特徴:CO₂をほとんど排出せずに製造された素材やエネルギー
- 🟢「理想的だけどコスト高」
✅ ブルー(Blue)
- 由来:化石燃料由来だが、排出されるCO₂を回収・貯留(CCS)している
- 例:ブルー水素、ブルースチール(表記は少ないが使われることも)
- 特徴:CO₂排出はあるが、大部分を回収することで実質削減
- 🔵「現実的な過渡期の選択肢」
✅ グレー(Gray)
- 由来:化石燃料由来で、CO₂回収もしていない
- 例:グレー水素、グレースチール(ほぼ“従来型”)
- 特徴:最も一般的かつ安価だが、CO₂排出量が多い
- ⚫「従来型/脱炭素ではない」
日本製鉄の「NSCarbolex Neutral(エヌエスカーボレックス・ニュートラル)」は CO₂排出ゼロをうたった日本製鉄のグリーンスチールブランドですが、特別な方法を用いて製造しているわけではなく、同社が脱炭素施策として全体で取り組んで得られたCO2削減量を社内でプール(貯金)し、それをグリーンスチール(NSCarbolex Neutral)に割り当てて「実質CO₂ゼロ」の製品として提供しているものです。
その根拠や算定方法については、国際基準に準拠した第三者の認証・監査を受けており、4月にはいすず自動車のEVトラックや実験棟の建設部材にも採用が決まっています。
グリーンスチールはJFEスチール、神戸製鋼所などもそれぞれに異なる技術で取り組み、自動車部品などに採用されていますが、そのうちJFEスチールのCMには我らが宮城出身のお笑いコンビ”サンドウィッチマン”が出演していい味?を出していますので、そちらもぜひご覧ください。
【CM】2025① 地球にやさしい鉄篇/30秒ver.(JFEスチール)
石炭を使わず水素を使う水素還元製鉄方式

鉄鋼業は世界のCO₂排出量の7〜8%を占めると言われています。1トンの鉄を作るのに排出されるCO2はなんと1.8トンで、これはガソリン車(普通車)約9,000kmの走行分と同じで、日本縦断(北海道宗谷岬~鹿児島県佐多岬/約2,500km)を約3.5回分走る距離に相当します。
パリ協定や各国・各企業のカーボンニュートラル宣言などで「2050年までに実質ゼロ」が世界的なスローガンになっている今、鉄鋼業界も例外に漏れず対策が求められていますが、中でも新しい技術として注目されているのが、水素還元製鉄です。
従来の製鉄プロセスは鉄鉱石に含まれる酸化鉄(Fe2O3など)に石炭(コークス)の炭素(C)を反応させて還元(酸素を除去)し、銑鉄(Fe)と二酸化炭素(CO2)に分離するものでした。
この石炭(コークス)の代わりに水素を使って還元(酸化鉄から酸素を除去)すれば、二酸化炭素のかわりに水(H2O)が排出されるので、理論上は温室効果ガスが発生しないということになります。
このとき使用される水素が再エネ由来のグリーン水素であれば、完全にカーボンフリーの製鉄になりますが、そう簡単にはいきません。
現時点では化石燃料由来の水素(グレー水素)が一般的であり、安価なグレー水素に比べグリーン水素は高額であるうえに供給も不安定だからです。
しかし現実には、スウェーデン、ドイツ、オーストラリアなどでは量産を目指す企業が活動を開始しており、スウェーデンのSSAB社はすでにボルボグループにグリーンスチールを納品しています。
BMWやベンツ、イケア、Appleも導入、高いのになぜ?
スウェーデンでは、
・鉄鋼のSSAB社
・鉱山会社のLKAB社
・再エネ由来の電力と水素を供給するVattenfall(バッテンフォール)社
の三社がタッグを組み、Hybrit(ハイブリット)というプロジェクト名で、グリーン水素によるグリーンスチール製造を行っています。
Hybritの水素は再生可能エネルギーの電力で水を電気分解したものですが、電気分解による水素製造は大変コストがかかるうえに、プラント全体の設備にも多額の投資が行われているため、このプロジェクトで提供されるグリーンスチールは従来品よりかなり高く、ボルボグループに納品した製品は従来鋼の2〜3倍のコストと推定されています。
ヨーロッパにはほかにもH2 Green Steel(スウェーデン)やSalzgitter (ザルツギッター/ドイツ)など、グリーンスチールを供給している企業がありますが、いずれも20~40%割高です。
それでもBMWやメルセデスベンツで部品や構造材の一部に採用され、IKEAでも什器などに導入。また2023年にはAppleがiPhoneやApple Watchの部品にグリーンスチールを使用したことを発表しました。(ということは、あなたのiPhoneやAppleWatchにもグリーンスチールが使われているかもしれませんね。)
高額でも世界の大手企業が導入を進める背景にはブランド価値を高めるだけでなく、「これからはCO₂を出すとお金がかかる時代が来る」と感じているからです。
EUでは製品を外国から輸入する際に「製造でどれだけCO₂を出したか」をチェックして、高炭素の商品には追加で課税する制度(カーボン国境調整)が2026年に始まろうとしています。
カーボン国境調整の対象は「セメント、鉄鋼、アルミニウム、肥料、電力、水素」の6品目ですが、ここに鉄が含まれているため、ヨーロッパでは今のうちからグリーンスチールを導入しておかないと後で不利になるかもしれないという空気があります。ですがサプライヤーは現時点でほんの数社。そこで大企業では小さなところから段階的に採用し「早めにツバを付けておきたい(?)」のかもしれません。(グリーンスチール製造各社にはほかにも多数の契約申し込みが来ているそうです)
カーボン国境調整は脱炭素の規制が厳しいEU製品とゆるい国からの輸入品を比較してCO2削減コストの差額を埋める施策とも言えますが、同様の施策を米国も検討しており、これらは日本の鉄鋼業にも影響を及ぼすと見られています。
つまり今後は、脱炭素製品でなければ輸出上の競争力を失うことになるため、国内企業もまた、グリーンスチール技術の向上と量産化に向けて走らざるを得ない状況になってきました。ところが再生可能エネルギーが豊富なヨーロッパと異なり、国土が狭く再エネ設備の規模が小さい日本ではグリーン水素の安定調達がさらにいっそう厳しく、設備にも巨額の資金が必要となることから、各社では日本でも持続可能な方法を目指して模索を続けているようです。
(ミカドONLINE 編集部)
参考/引用記事: いすゞ、国内で初めて商用車の原材料にグリーンスチールを採用 ~2026年に稼働開始予定の電動開発実験棟「The EARTH lab.」にも1,000トンを使用~ | いすゞ自動車 グリーンスチール「NSCarbolex Neutral」のいすゞ自動車株式会社のエルフEV及び電動開発実験棟「The EARTH lab.」への採用について GI基金事業 製鉄プロセスにおける水素活用の概要と進捗状況[PDF] NSCarbolex Neutral – NSCarbolex® [エヌエスカーボレックス] | 「社会全体のCO2削減に貢献する製品・ソリューション技術」の総称ブランド 日本製鉄、グリーンスチール「NSCarbolex Neutral」がいすゞのエルフEV及び電動開発実験棟に採用 – 日本経済新聞 など
ー 記事一覧 -