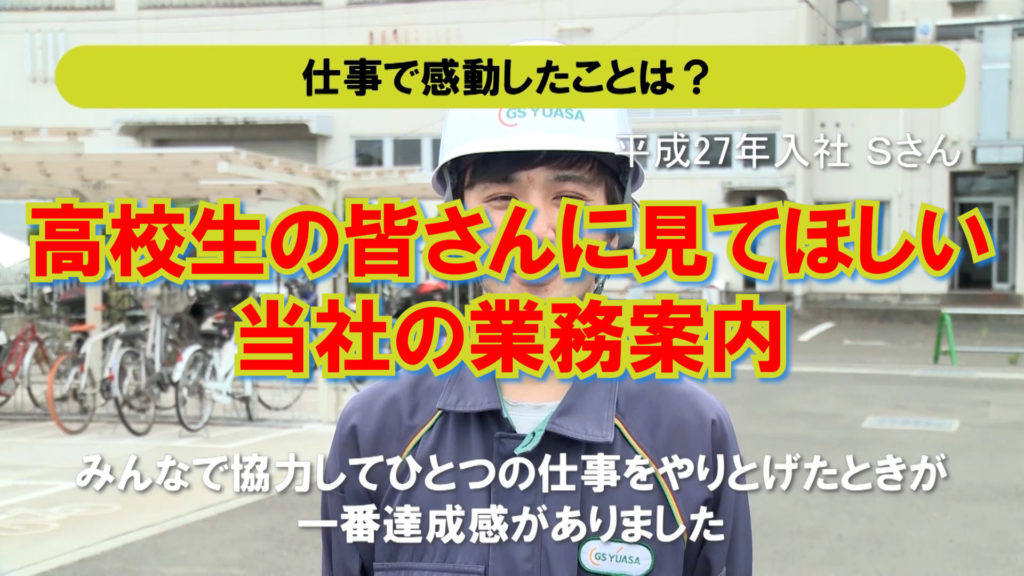道ばたや畑のすみに、赤い粒をびっしりと並べた小さな草を見たことはありませんか?どこにでもある雑草のようですが、実は子供の遊びや暮らしの中で親しまれた歴史を持っています。今回はそんな身近な雑草「イヌタデ」を取り上げます。
踏まれても立ち上がる、赤い点線の草

イヌタデはタデ科の一年草で、日本全国の道ばたや畑、空き地など、いたるところで見られます。高さは20〜40センチほど。夏から晩秋にかけて赤い小花をびっしり咲かせ、細長い穂を赤い粒で埋め尽くします。
近くでよく見ると、花びらに見える部分は実は萼(がく)で、ひとつひとつはとても小さな果実です。ですが群れをなすと地面に赤い線を描くように広がり、風景の中で意外な存在感を放ちます。
踏まれてもすぐに立ち上がる丈夫さも特徴の一つです。
「役立たず」と呼ばれた名前の由来
「イヌタデ」という名前には、ちょっと切ない背景があります。

「タデ」と呼ばれる植物の仲間には、強い辛みをもつ「ヤナギタデ」があります。これは昔から薬味や香辛料に使われ、人の暮らしに役立つ植物でした。
(ヤナギタデの画像)
ところがイヌタデは、見た目は似ていても辛みがほとんどありません。そのため「役に立たないタデ」という意味で「イヌ」が冠され、「イヌタデ」と呼ばれるようになったといわれています。昔の人にとって“イヌ”は「劣る」や「無用」を表す言葉だったのです。
その一方で、赤い花穂を子供のままごとで赤飯に見立てて遊ばれていたことを由来に、「アカマンマ」という別名も持っています。若菜や花穂は、アク抜きを行えば天ぷらや和え物、ふりかけにして食べることもできます。(イヌタデ自体にほとんど味は無いそう)
また、イヌタデは秋の季語として俳句にも詠まれてきました。小さな赤い穂が連なる姿は、秋の野に点々と色を添える情景として、文学の中にも残っています。
花言葉は「あなたのお役に立ちたい」。名前の由来から考えるとなんとも悲しい花言葉です。
しかし、役立たないと切り捨てられた名前とは裏腹に、人の暮らしや文化の中で確かに息づいてきた植物なのです。
(ミカドONLINE編集部)
参考/引用 農業・食品産業技術総合研究機構(NARO)-イヌタデ など