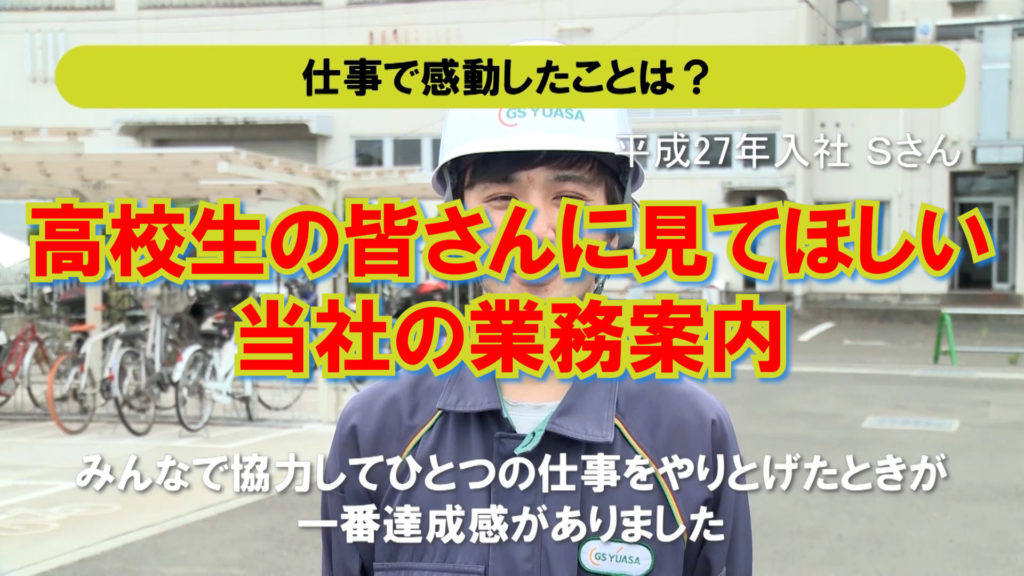深海域でも設置可能な「浮体式洋上風力発電」が、ついに国内で初めて稼働しました。これは日本のエネルギー政策にとって歴史的な節目と言われています。今回はその理由や背景について深堀りしてみます。

浮体式洋上風力発電とは? ― 日本に必要とされた理由
再生可能エネルギーの普及が急務となる中、日本でついに「浮体式洋上風力発電」が初めて稼働します。
この取り組みは、国立研究開発法人 NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構) が支援する実証事業の一環として進められ、戸田建設、日立造船、商船三井、九電工 など国内有力企業が共同で事業主体を担っています。
この計画では現在、商業運転中の実証機と合わせて計8基の巨大な風車が建っている長崎県五島市の「五島洋上ウィンドファーム」に残り1基を追加し、2026年1月から本格的な運用を目指すものです。
浮体式洋上風力発電は、海に浮かぶ大きな台の上に風車を建てて、係留索やアンカーで固定する仕組みです。これにより支柱が届かない水深200mを超える沖合でも設置が可能になり、安定した強い風を活用できます。陸地から遠く離れることで景観や騒音の影響も軽減されます。
世界ではノルウェーやイギリスが先行し、特にノルウェーの「Hywind」が商業運転に成功しています。日本でも2010年代から実証実験が進められてきましたが、今回の初稼働は「商業化に向けた本格始動」と位置づけられています。
注目されるのはなぜ?
浮体式洋上風力が注目される理由は次の三点です。
- 立地の自由度が高い
水深200mを超える海域でも設置可能。日本近海のような急深地形でも大規模導入が現実的になります。 - 発電効率が高い
沖合は風況が安定しており、強い風を継続的に利用できるため発電量の増加が見込めます。 - 景観・騒音への影響が少ない
沖合に設置できるため、陸上からの景観への影響や騒音問題を最小限に抑えられます。
技術革新と経済効果 ― 地方創生の可能性
浮体式の実用化には「安定性を確保する技術」が不可欠です。荒波や台風に耐えるため、世界的にはいくつかの構造がすでに開発されています。
- スパー型:円筒を深く沈め、浮力と重心で安定。
- セミサブ型:複数の浮体でバランスを取る方式。
- テンションレグ型:海底に強く係留し、揺れを抑える方式。
しかし過去に北九州市沖で設置された実証機『ひびき』は、上記のいずれにも属さない平らな台船のような“バージ型”で、日本初の本格的な浮体式風力発電の実証として知られています。
そして今回の稼働設備もまた、それらを参考にしつつ 日本の海象条件(台風・津波・急深地形)に特化した設計 が採用されています。そのため現時点では過去の「何型」にも属さない独自形式のようです。
特徴的な日本の海で浮体型を実用化するためには、気象と地形により特化した新たなスタイルが必要になってくるのだと思います。
また浮体式の実用化で経済的な効果も期待され始めました。造船業、港湾業、鉄鋼業、建設業など幅広い産業に関連し、新しい雇用を生み出すからです。そのため東北の沿岸地域でも、再エネを核にした地域振興の可能性が現実味を帯びてきました。電力の地産地消が進めば、地域の自立性向上にもつながります。
具体的には秋田県南部沖の実証事業が2029年の稼働を目指して進行中ですし、岩手県の久慈市沖でも水深70~110mの海域を対象に浮体式洋上風力発電の導入可能性を検討中です。
課題と展望 ― 「小さな一歩」で「大きな飛躍」へ
一方で課題も残ります。最大の壁は「コスト」で、浮体や係留システムの製造・設置費用は依然として高額です。ただし、大規模導入による量産効果と技術革新により、今後は確実に低減していくと見られています。
また、日本特有の台風・地震への対応、長期運用のためのメンテナンス体制構築も不可欠です。これらを克服した経験は、将来海外展開を図る際にも競争力となるでしょう。
政府は2030年代に数千万kW規模の洋上風力導入を目指しており、浮体式の初稼働はその壮大なロードマップのスタートラインです。地球温暖化対策、エネルギー安全保障、地域経済振興という三つの課題を同時に解決する可能性を秘めている浮体式洋上風力発電は、今後大きな台風の目となりそうです。ぜひ本物の「台風」に負けることなく、着実に地位を築いてほしいものですね。
(ミカドONLINE 編集部)
参考/引用記事: 「浮体式」洋上風力が国内初稼働へ 世界最先端の技術、日鉄系など投資 など
ー 記事一覧 -