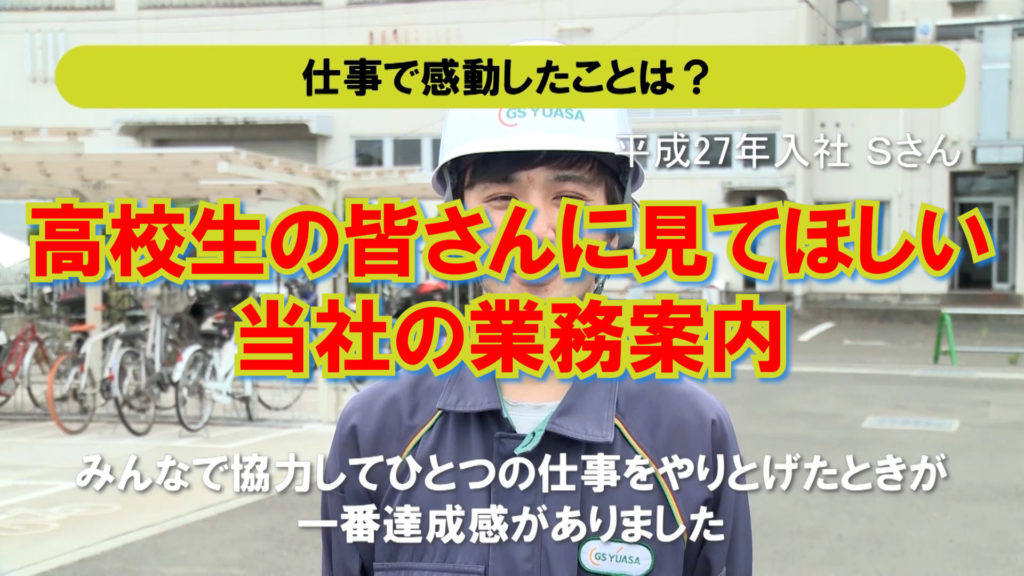先に人口光合成の記事を掲載しましたが、その中で取り上げた光触媒は本来の開発目的とは違う分野で世界中に普及し、いまでは産業界になくてはならないものになりました。今回は応用範囲が多岐に渡るせいで、イマイチよくわからなくなってきた光触媒について解説します。

広い分野で実用化されている光触媒
先の記事で人口光合成について取り上げ、太陽光で水を分解して酸素と水素を発生させるためには光触媒が必要であることをお伝えしました。
(過去記事)人工光合成とは?~植物のしくみをまねて水とCO2とおひさまの光で水素をつくろう!~
触媒とは自分自身は変化せず、自分と接触(直接/間接)している物質のほうに化学反応を起こさせる素材のことを指します。現在開発されている人口光合成は、光触媒シートと水分解パネルで酸素と水素を取り出すしくみです。
実は、光触媒にはエネルギー分野よりも先に実用化されて、世界中に普及するきっかけとなった二つの大きな特徴があります。それは、強い分解作用と超親水作用です。
光触媒の正体は酸化チタンという物質ですが、酸化チタンに光を当てると電子が急速に活発化して飛び出し、これが他の物質の分子と結びついて相手を酸化・分解します。
その作用がとても強く、光触媒はアルコールや植物の葉や小さな虫までも炭素と水に分解してしまうそうです(ただし虫の分解には年月がかかるとのこと)。そのため技術の確立まで時間を要する「水を分解する能力」よりも、まずこの機能を最初に活かして、除菌、抗菌、除ウイルス、抗ウイルス、防カビ、防汚、消臭等の諸製品に使われるようになりました。

また光触媒は、光を当てると自分に触れている他の物質を親水性のように変化させる不思議な働きがあります。
光触媒をコーティングしたガラス窓はたとえ油で汚れても、雨が降ると油汚れが水に馴染んで流れてしまうので、今では多くの建築物に使われています。
光触媒による水の分解を最初に発見したのは日本人ですが、この方法で大量の水素を得るには無理があり、結果的に本来の目的とは違う方向で普及させたことが、光触媒をわかりにくくしている原因のひとつだったのです。
本多・藤嶋効果の発見~脚光と衰退~

1967年、東京大学の大学院生だった藤嶋昭氏(東京理科大学第9代学長、東京理科大学栄誉教授)は写真フィルムの現像について研究をしており、白金の電極と様々な半導体素材の電極を線で繋いで水に入れて光を当てる実験を繰り返していました。

光に感応しやすい材料を探すためのこの実験では、シリコンやゲルマニウムは溶けて使い物になりませんでした。
そこでコピー機を研究していた隣の研究室から情報を得て酸化チタンを取り寄せ試してみると、電圧を何もかけないのにそれぞれの電極から違う気体が発生したのです。
調べてみると酸化チタン側からは酸素、白金側からは水素が出ることがわかり、藤嶋氏は興奮しました。水を酸素と水素に分けるためには電気分解しかありえないと考えられていた時代に、電気を使わなくても分解できる方法を世界で初めて発見したからです。
しかし光がエネルギーだという概念がまったくなかった昭和の当時、この発表は国内で全く受け入れられず、むしろ「勉強不足」という大きな批判を浴びる結果になってしまいました。

そこで恩師の本多健一博士(1925年 – 2011年)と共著でイギリスのネイチャー誌に論文を投稿したところすぐに採用が決まり、「本多・藤嶋効果」と名付けられたこの現象は世界中に知れ渡ることになりました。
世界が注目したのはこの現象で発生する水素です。オイルショックで石油依存に不安を感じた各国はこの頃から代替エネルギーを模索し始めており、当時から候補として有力視されていた水素が地球上に豊富にある水から得られる方法としてにわかに脚光を浴びたのです。
けれど太陽光のうち紫外線だけが有効活用されるこの方法は、水素の大量生産に向かず大きなコストもかかるため、研究は行き詰まりやがて停滞していきました。
東大の汚いトイレでひらめいた!

酸化チタンは白色顔料として白ペンキや化粧品などに使われているありふれた素材です。それが光触媒という世紀の大発見として、新聞にも取り上げられる研究の目玉になったのですから一時は大きな話題になりました。
ですが効率やコストの面で難点があり、過去にエネルギーとしての実用化に至らなかったのは前述のとおりです。発見者の藤嶋氏もエネルギー活用にはいったん見切りをつけ、新しい活用方法を模索することになりました。
ここで転機になったのは研究室に新たに加わった橋本和仁氏(当時は東大講師)の存在です。
光触媒としての酸化チタンに強い酸化・分解作用があることはすでにわかっていましたが、同氏はそれを「汚れのつかないトイレ」に活用できるのではないかと考えたのです。
きっかけは東京大学のトイレでした。橋本氏は東大の汚いトイレを利用したときに、「光触媒がなんでも酸化・分解してしまうのならトイレの汚れも分解できるのでは?」と考えたそうです。
そこでツテをたどってTOTOの担当者と出会い、話し合いの末、光触媒はトイレではなく抗菌タイルとして製品化していく方向性になりました。(「汚れのつかないトイレ」はすでにTOTOが別の技術で商品化していたため)
そして研究開発の過程で新たな事実もわかりました。それは光触媒には自分に触れているものを水と馴染ませてしまうような超親水性の効果があるということでした。また光触媒には表面張力による水滴をつくらず透明なガラス面を常にクリアに保つ機能があることもわかりました。
こうやって光触媒は、病院などの光触媒抗菌タイルや、防曇・防汚のコーティング材として広く普及していきました。
一周回って人口光合成として再び注目

紆余曲折を経て今に至る光触媒ですが、技術革新が進んだ現在は、人工光合成の要として再び重要視され始めています。実は、似た材料の中でなぜ酸化チタンだけが特徴的な動きをするのか?は、まだよく解明されておらず、いまも熱い議論のテーマになっているそうです。
けれど世界の常識を覆した「本多・藤嶋効果」の発見者である藤嶋氏はノーベル賞候補と言われるようになり、いま最前線で人工光合成の実用化を研究している堂免一成氏(東京大学教授、信州大学特別特任教授)もノーベル賞候補者として世間に名前が挙がるようになりました。
光触媒は日本が先行する技術ではありますが、各国も激しく追随してきているのは先の記事で書いた通りです。
いまはそれぞれの国が競い合い切磋琢磨することで、新しい技術が確立していく過程にあるようです。「必要は発明の母」と言いますが、「競争は発明のエネルギー」と言えるのかもしれませんね。
(ミカドONLINE編集部)
引用・参考 光触媒 | 酸化チタン光触媒コーティング|日建総業 もうちょっとでノーベル賞!?『世紀の大発明!光触媒』 – 株式会社RUMMY 藤嶋昭先生第3回|研究者|みらいぶっく|学問・大学なび|河合塾 など